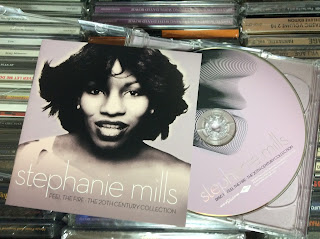スティーブ・コールマン&ファイブ・エレメンツとしては三枚め。ケヴィン・ブルース・ハリス(Kevin Bruce Harris)のベースに、マービン・スミッティ・スミス(Marvin “Smitty” Smith)のドラム、デヴィッド・ギルモア(David Gilmore)のギター。斬り込んでくるホーン隊。
アレンジだの演奏だの、ダレる一瞬もなく。耳をそばだてさせる、カッコ良さ。
Dave Holland Trio “Triplicate”
そして、“Sine Die” と同じ1988年に録音された一枚。こちらはジャズ。
ベースのデイヴ・ホランド(Dave Holland)、ドラムはジャック・ディジョネット(Jack DeJohnette)。1968年に電化マイルス組に参加、あの “Bitches Brew” でもやったベテラン二人と、スティーブ・コールマンという三角形。
デイヴ・ホランドは、80年代を通じて幾度もスティーブ・コールマンを招いては共演しています。
自身のグループではクールにクールに、スタイルを徹底しているスティーブ・コールマンですが、こちらの土俵となると、手数の多い先輩達がぐいぐい来ますから。ピアノなし、三人だけの研ぎ澄ました演奏、やり取りが聴きものです。美しいスローな曲があったりも。
なお、スティーブ・コールマンの初リーダー作 Steve Coleman Group “Motherland Pulse”(1985)を聴いてみると、彼のジャズからファンクに至る過程が垣間見れるような楽しさ。