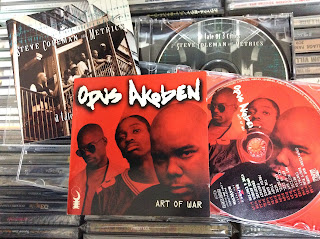2020年で20作め、“XX” と書いてトゥエンティと読む、というブライアン・カルバートソンのアルバム。
ブーツィーをゲストに招くのは、アルバム “Bringing Back The Funk”(2008年)以来の二度め。この間には、“Funk!”(2017年)というそのままのタイトルを持ったアルバムもありますから、相当にお好きであります。
今回はまたストレートな明朗明快パーティ・チューン。ブーツィーはボーカルを乗っけたのみ。
前回の共演では、ブーツィーのスタジオにて録音、バーニー・ウォーレル(Bernie Worrell)にキャットフィッシュ・コリンズ(Phelps “Catfish” Collins)、それにフレッド・ウェズリー(Fred Wesley)、メイシオ・パーカー(Fred Wesley)らも参加という濃厚さでしたが。
アルバム制作の顔ぶれには、相当に腕達者のプレイヤー達が集められているようです。とはいえファンクの奥の細道、藪の中みたいな深さは、カケラも見せません。ブーツィーとの初共演から10年ちょっと経ったからといっても、この2020年だからといっても、徹底して匂わせもせず。